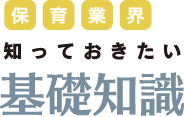 |
| 幼保一元化とは |
現在、就学前児童の教育・保育施設として、厚生労働省が管轄する「保育所(保育園)」と文部科学省が管轄する「幼稚園」の2つがあることは、皆さんもよくご存知のことでしょう。この2つを一緒にしようとする動きが「幼保一元化」です。
|
 |
 |
 |
| |
社会的変化に対応し機能が接近する保育所と幼稚園
もともと保育所と幼稚園は、保育所が児童福祉法で定める「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または、幼児を保育する」児童福祉施設であり、幼稚園が学校教育法が定める「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長する」学校教育施設であることから、まったくの別のものでした。
ところが、1990年代から顕著になる少子化や女性の就労率の高まりといった社会的変化により、両者の機能は接近してきます。少子化で園児が減少した幼稚園では、働く母親の要望を受け入れる形で長時間園児を預かる「預かり保育」をスタート。一方、保育所でも、保護者の多様化するニーズに応えてサービスの向上が図られたのです。結果、両者の違いはほとんどないものになりました。
こうした状況に財政難に悩む地方自治体では、保育所と幼稚園を一体化して運営を効率化しようとする動きが出てきます。しかし、所管や申請、保育料、補助の仕組み等の制度上の違いが大きな障害になったことから、一元化の要求が出されるようになったのです。
自治体の一元化要請を受け認定こども園制度がスタート
自治体からの一元化要求に対して、当初、厚生労働省と文部科学省は「両施設にはそれぞれ異なる機能・役割があるため一元化は困難、運用の改善により、両者の連携強化を推進することで、一体的な運営が可能」と反対。施設の共有化だけを認める指針を1998年3月に出すことになります。それでも、地方自治体では構造改革特区制度を活用して幼保一元化関連の申請を多数行うことで、一元化を推進していきます。
こうして自治体による幼稚園と保育所の一体的運営の取り組みが先行する中、政府の「骨太方針2003」で打ち出されたのが、総合施設、すなわち今日の「認定こども園」構想です。この方針の中で総合施設は、「近年の社会構造・就業構造の著しい変化等を踏まえ、地域において児童を総合的に育み、児童の視点に立って新しい児童育成のための体制を整備する観点」から「地域のニーズに応じ、就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した施設」と説明されていました。
これを受けて厚生労働省も文部科学省も、それぞれに総合施設の検討を開始。両省の間で幼児教育課長と保育課長の初の交流人事も行われるなど幼保連携を深め、2006年10月から認定こども園がスタートすることになったのです。
地域の実情に対応して4つのタイプを認定
この認定こども園は、保育所および幼稚園等における就学前の子どもに対する保育および教育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設として、都道府県知事が条例に基づき認定することになっています。
また、地域の実情にきめ細かく対応するため、認定幼稚園と認定保育所が連携した「幼保連携型」、認定幼稚園が保育所的な機能を備える「幼稚園型」、認定保育所が幼稚園的な機能を備える「保育所型」、幼稚園・保育所いずれの認可もない地域における「地方裁量型」の4つのタイプが認められています。
幼保連携推進室のホームページによれば、2009年4月1日現在、全国で358施設(43都道府県)が認定こども園の認定を受けています。 |
|
 |
 |
 |
| 近年の少子化への対応として、「幼保一元化」は小泉政権の構造改革の一環として進められてきましたが、2009年10月、鳩山内閣はこの動きをさらに加速させる方針を固めました。行政刷新会議では、現行の「認定こども園」の認定基準の緩和や手続きの簡素化、地方自治体の担当部署の統一促進などが検討される見通しで、文部科学省と厚生労働省の二重行政解消にも踏み込む構えだそうです。 |