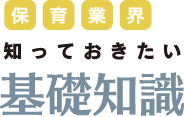 |
| 「新保育所保育指針」の適用スタート |
| 2008年3月28日に舛添厚生労働大臣により告示されていた新しい「保育所保育指針」、今年4月1日からいよいよ適用が開始されました。この新指針は、2006年12月に改定に関する検討会がスタートして以来、ワーキンググループの作業と検討会主査の会議を除き、基本的に公開のもとに行われてきたものです。告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるよう、厚生労働省から「保育所保育指針解説書」も出されています。 |
| 全国の園長先生に「就職前に読んでおいてほしい本はありますか」とアンケートをとったところ、「保育所保育指針」と回答された園長先生が多数いらっしゃいました。現在では様々な解説本も出版されていますので、保育園に就職を希望される方は、一度目を通しておいてもよいかもしれませんね。実際に、現在保育園で働いている職員さんたちも、保育園の内外で指針改定にともなう研修会や勉強会を行っているようです。 |