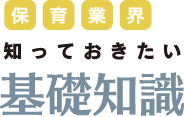 |
| 保育園の規制緩和 |
自民党政権から民主党政権へと代わり、今後保育業界はどうなっていくのでしょうか…?
今後のことを考えるためにも、今回は、これまでの自民党政権時代に進められてきた保育園の規制緩和について記したいと思います。これから保育士をめざす皆さんにとっても、これまでにどのような規制緩和が進んでいるのかは、当事者として知っておくべきことでしょう。
|
最後に
民主党のマニフェストでは政策各論14において、
保育所の待機児童を解消する
【政策目的】
○縦割り行政になっている子どもに関する施策を一本化し、質の高い保育の環境を整備する。
【具体策】
○小・中学校の余裕教室・廃校を利用した認可保育所分園を増設する。
○「保育ママ」の増員、認可保育所の増設を進める。
○「子ども家庭省(仮称)」の設置を検討する。
とあります。
保育業界には待機児童を始め、教育の問題や保育士不足などさまざまな問題が蓄積されています。
民主党政権となり、今後保育業界がどのような変化していくのか注目していきましょう。 |