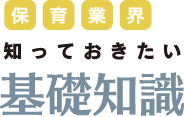 |
| 「新待機児童ゼロ作戦」が現在進行中 |
| 「待機児童」とは、「保育所(認可保育所)に入所することを希望し、入所資格を有するにもかかわらず、当該市区町村域内の保育所の施設定員を超過する等の理由で入所ができない状態にある児童」のことです。国では、少子化対策の一環として待機児童をなくす努力をしていますが、なかなか減らないことから、2008年2月に「新待機児童ゼロ作戦」を発表しました。 |
 |
 |
 |
| |
なんで「新」って付いてるの?
昨年発表された作戦に「新」と付いているのは、それに先立つこと7年前の2001年から最初の「待機児童ゼロ作戦」が展開されていたからです。
2001年当時の状況
当時の就学前児童を取り巻く環境を振り返ってみると、、保育所への入所を希望しながら入れない待機児童が、全国で3万5000人あまりを数えました。それまでも少子化対策の一環として立案された「新エンゼルプラン」のもと、保育サービス等子育て支援サービスの充実が進められていたのですが、女性の就労率のアップや核家族化、子育ての孤立化など社会を取り巻く環境の変化から、入所できる児童数を増やす以上に入所を希望する児童数が増えていたのです。
待機児童ゼロ作戦の発令
そこで打ち出されたのが最初の「待機児童ゼロ作戦」です。保育所の整備や自治体単独施策、幼稚園の預かり保育などを活用し、2002年度中に5万人、さらに2004年度までに10万人、計15万人の受け入れ児童数の増大を図り、待機児童をゼロにしようという目論見でした。
その結果として
実際、こうした施策を受け、入所できる児童数は2004年度の時点で目標に近い14万人増を達成しました。ところが、女性の労働力人口の増加や都市部の再開発による住宅建設などにより、特定の地域において保育需要が急増したことから、なお2万4000人あまりの待機児童が発生し、作戦名通りゼロにはなりませんでした。
新待機児童ゼロ作戦の発令
その後も入所を希望する児童の数は増え続け、それに伴って待機児童の数も再び増加するようになります。そこで厚生労働省は2008年2月、再び待機児童をなくすための「新待機児童ゼロ作戦」を発令することになったのです。
目的
その目的は、「希望するすべての人が子どもを預けて働くことができるためのサービスの受け皿を確保し、待機児童をゼロにする」ことで、10年後の数値目標として「保育サービス(3歳未満児)の提供割合38%(現行20%)、利用児童数(0〜5歳)100万人増」を掲げました。
具体的な施策
そして、それらを実現するための具体的施策として、「保育サービスの量的拡充と保育の提供手段の多様化」、「保育サービス等の計画的整備」、「認定こども園の設置促進」など「地域や職場の実情に応じた取組の推進」、「質の向上等に資する取組の推進」などを打ち出したのです。
現在、新待機児童ゼロ作戦は、3年間の集中重点期間中であり、その成果が注目されています。
実際に2009年6月に、厚生労働省と文部科学省は、保育士資格と幼稚園教諭免許を相互に取得しやすくために、条件を緩和する方針を明らかにしました。保育所に入所できない待機児童がいる一方で、幼稚園に入園する子どもは減少傾向にあることを踏まえた、幼稚園に保育園の機能を持たせたタイプの「認定こども園」を増やすことで待機児童の解消につなげたいとの考えからです。認定こども園の職員は幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を取得していることが望ましいとされています。それゆえに幼稚園教諭免許と保育士資格の垣根を低くしようと、今まさに動き出したところなのです。
|
|
 |
 |
 |