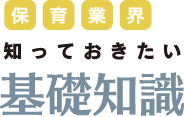 |
| 少子化と保育園 |
これまで、保育業界に関する政策などを紹介してきましたが、ここで改めて、現代の日本が抱える「少子化」についてのお話をしておきたいと思います。
|
 |
 |
 |
| |
出生率の低下で総人口が減少
もともと日本では、合計特殊出生率は1973年の第二次ベビーブームの2.14を境に減り続けています。そして、1989年の人口動態統計では1.57となり、1966年の1.58をも下回ったために社会的関心を集めることになったのです。その後も、この合計特殊出生率の低下は続き、2002年度の国民生活白書で「少子化」という言葉が使われ、一般に広まることとなりました。
2005年の国勢調査によると、合計特殊出生率は1.27とこれまでの最低になったほか、総人口の減少も始まりました。人口を維持するためには、合計特殊出生率はおよそ2.08が必要と言われ、人口が減少することは国力の源泉の減少でもあり、望ましいものではありません。そこで、行政でもさまざまな少子化対策を打ち出しているのです。そのなかには保育園に関連したものも少なくありません。
合計特殊出生率:一人の女性が一生に産む子どもの数
原因は女性の社会進出や教育費
こうした少子化の主な原因として挙げられるのが、晩婚化や無産化です。未婚化や晩婚化が進んでいる上に、結婚した場合でも経済的理由により子どもが生まれたときの十分な養育費が確保できる見通しがたたないと考え、出産を控える傾向があるのです。
実際、国民生活白書によれば、子ども一人に対し1300万円の養育費がかかると言われています。しかも、この額は基本的な生活費だけのもので、そこに教育費を含めると2100万円になるというのです。これでは、子どもを産むのを控えたくなるのも無理はありません。
また、女性の社会進出が増えたことも、出生率の低下につながっているとの指摘もあります。日本では、子育てを支援する制度が十分でないので、子どもを産むと仕事が続けられなくなる可能性が高いと言われています。
少子化にも関わらず増加傾向の保育園
しかし、保育園の数は少子化の影響を受け、1985年から減少していましたが、2000年を境に増加に転じています。特に増えているのが民営の保育園で、最も少なかった1995年の9,304施設が2008年には11,581施設と実に約25%も増加しているのです。
少子化にも関わらず民営の保育園が増えている背景としては、先ほど述べた女性の社会進出の増加が挙げられます。また、都市化や核家族化により、家庭での子育てに不安や負担を感じる親が増えたこと、家族や地域だけでは社会性を身につけることが難しくなってきたことなども原因になっていると考えられます。
このように保育ニーズの増加に応えて数を増やしている保育園ではありますが、人口増加の多い首都圏や近畿圏では、保育園の整備が間に合っていないというのが実情です。少子化の時代だからこそ、保育園に求められる役割は大きくなってきているのです。
|
|
 |
 |
 |